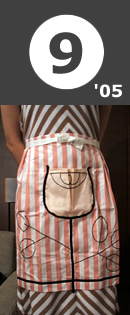/ 13 Sep. 2005 (Tue.) 「靖国問題」
■ここのところ友人・知人のサイトをまめにチェックしておらず、たとえば「上山君の日記、読んだ?」と妻に聞かれてはじめてそれを見に行き、ようやく今日「1 1/2計画」の告知を知ったような感じである。
■しかし上山君(夫妻)の日記といえば、まったくいまさらながら言及しておきたいというのは8月15日付けのそれで、つまりふたりはその日、また別の友人に誘われて靖国神社に参拝に行ったのだった。そのことに関して、サイトではふたりがそれぞれの視点から別の日記を書いているが、
境内に入る門をくぐったところで、まもなく正午ですから、黙とうをしましょう、というアナウンスが入る。それが耳に入った途端、反射的に、走って逃げてしまった。
と書く恭子ちゃん(上山夫人)が、つづけて、
日本の首相が靖国神社にお参りすることについて他の人がいろいろなことを言うのを、私はあまり快く受け止められない。靖国神社にお祀りされている人が、どんな人だったか、ということが、問題になっている。でも、人は死んだら、物になるだけだ。土とか、水とか、空気になる。そして、あたらしい命はそこから生まれる。私も、そうして生まれた。だから、それはとても尊いものだ。そういうことを宗教の言葉では、死んだら仏になるとか、カミになるとか言うのだと、私は思っている。
と書くのを読みながら、私は正直なところ苛立ったのだった。そうじゃないんだよ。「靖国問題」というのはそういうことじゃないだ。ひどく「良心的」に見える上記のような言説のなかに問題が回収されてしまうとき、それは結果として「靖国の精神」と呼ばれるあの嫌悪すべき思想(「お国のために」という言葉に表される思想)に与してしまうことにしかならないのだ、と。けれども、そのように苛立つのは少し気が早かった。恭子ちゃんは次のようにつづける。
けれども、そういう死んだ人に会いに行こうというときに、「国」という言葉が出てくると、抵抗がある。よく分からないけど、死んだ人に直接関われなくなるように感じる。靖国神社は奥に進めば進む程、「国」という言葉に満ちていた。たしかに、「国」というものは、ある。「太平洋戦争」もあった。「8月15日」もあった。その続きに私があることは、知っている。でも、人間は「国」じゃない。「太平洋戦争」でもない。「8月15日」でもない。とにかく、ここに眠っている人たちがいるのだ、その人たちに会わなければいけない、と思った。
それで、黙とうできなかった。
■いま、首相の公式参拝をめぐりその是非を問うというかたちで問題化されている「靖国問題」においてわれわれが問われているのは、つまるところ、「戦争がしたいの? したくないの?」ということだ。と書くと、「周辺諸国の抗議に対して断固たる姿勢を見せる(一戦まじえる)気概があるのか、穏便にすませたいのか」というニュアンスにとられる可能性もあるから厄介だが、むろんそういう意味ではなく、もっと根源的な問いとしての「あなたの家族・子供・知人を戦争に行かせたいのか、行かせたくないのか」である。
■まず基本的なところを確認しておきたいが、靖国神社に祀られているのは「すべての戦争被害者」ではない。広島・長崎の死者も、東京大空襲の被害者も、民間の死者たちは、いっさいそこには含まれていない。靖国神社が祀るのは「お国のために死んだ(と靖国側が判断した)軍人」だけである(そもそものはじめから言えば、明治維新直後、維新戦争をつうじて亡くなった「新政府側の戦死者」を慰霊するために建てられたのが靖国神社──当時は「東京招魂社」──である。そして言うまでもなく、「新政府側」というのは「天皇側」のことである)。また逆に、日本の植民地となった周辺諸国で「皇民化」を強制され、心ならずも日本軍として戦争に駆り出され戦死した日本人以外の人たちがそこには含まれている。その人たちが、死してなお日本の祭神として──その民族との関係において「加害者」である日本人と同列に──祀られることは故人にとって屈辱以外のなにものでもないとして、現地の遺族らが靖国神社に対し「合祀の取り下げ」を要求しているケースがあるが、靖国神社はそれらの要求にいっさい応えようとしない(これは少なくとも「一宗教法人」の振る舞いとは言えない)。
首相の靖国神社参拝について論じるときに、まず念頭に置かなくてはならないのは、現在も継続しているイラク戦争である。靖国神社であれ、別のかたちのものであれ、戦没者の追悼施設は戦争を遂行するための施設であって、首相の靖国参拝問題は、過去の歴史認識を巡る問題である以上に、現在と今後の戦争にかかわる問題である。靖国神社に関して小泉首相は「不戦の誓い」などという妄言を弄しているが、靖国神社の存在そのものがひとつの軍備であり、公人の靖国参拝が戦争準備行為であるという客観的な事実を見逃すわけにはいかない。国家の戦争を再生産するために戦没者は追悼されねばならず、生の再生産装置の傍らに死の再生産装置があるからこそ、男たちは徴用され兵士になることができるのである。ある皇軍兵士が軍事行動に際して「靖国で会おう」と誓い合ったという話が仮に事実だとするならば、それは明らかに戦争の誓いであり、靖国神社が戦争を推進する軍事施設としてあり続けてきたことを証明している。そのような腐った誓いを今後も可能にするのか、許容するのか、これからの若者たちにそのような誓いを強いるのかどうかが問われているのである。
──矢部史郎「六〇年前の亡霊にではなく、学生に賃金を。」(『現代思想』2005年8月号所収)
■いやまあ実際のところ、「靖国問題」にはものすごく多くの論点があるのであり(たとえば『現代思想』の「靖国問題」特集号には18本の論文と1本の対談が収められている)、その根幹にあるものはまちがいなく「戦争がしたいの? したくないの?」という選択だとしても、そのことを言い立てるだけではおそらく説明不足で説得力を欠くのだし、ほんとうはもっとじっくりと文章にしなければと思うものの、いくら「紙幅にかぎりのない」ウェブとはいえ1日分の「日記」──「日記」か、これは?──でまかなえるような問題ではないのであって、その意味でひとつ参考文献を挙げておくならば、むろんこれ、高橋哲哉『靖国問題』(ちくま新書) ![]() である。
である。
■同書の最終章において高橋は、靖国の「代替施設」として検討が進められている「(無宗教の)国立追悼施設」について考察を加え、そしてその結果、しごく単純な、単純であるがゆえに感動的ですらあるひとつの答えを取り出してみせる。『現代思想』に収められた対談のなかで高橋自身が説明している言葉を借りればそれは次のようなことである。
私は「国による追悼」を少なくともこの本(引用者註:『靖国問題』)の中では頭から否定しているわけではありません。「普通の国」による追悼は必ず「第二の靖国」になる、ということです。集団的追悼について言えば、人間の死、特に大量の死を様々な形で経験した共同体、それは家族から始まって地域社会や様々なレベルに及びますが、集団的追悼がそれ自体悪いとは言えない。国による追悼は一〇〇パーセント悪とも言えないだろう。しかしそれには条件がある。国による追悼が国家による顕彰となって、新たな戦争に国民を動員し、遺族に死を受け容れさせるための装置として機能する、つまり「第二の靖国」になるということであれば、反対せざるとえない。
そうならない究極の条件は、国家が常備軍を持たないことです。
──「討議 〈靖国〉で問われているもの」(『現代思想』2005年8月号所収)、太字強調は引用者
-
 お盆に実家に帰省した折りの写真ストックから。下も。
お盆に実家に帰省した折りの写真ストックから。下も。 -
 義姉の膝であそぶ姪。
義姉の膝であそぶ姪。 -
 必読。高橋哲哉『靖国問題』(ちくま新書)
必読。高橋哲哉『靖国問題』(ちくま新書) 。
。
関連記事
トラックバック(0)
このエントリーのトラックバックURL:
https://web-conte.com/blue/mt-tb.cgi/536