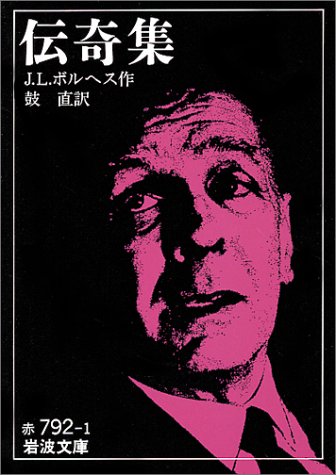/ 14 Jul. 2018 (Sat.) 「これぞ紛れもないフレニール──『枝分かれの青い庭で』」
■熊谷知彦ソロ・パフォーマンス『枝分かれの青い庭で』(作・演出:平松れい子)を観に、南青山のほうへ。かつては熊谷知彦好きとして知られたわたしだが、最近何公演かは見逃してもいて、ほんとうにすごくひさしぶりの熊谷さんだ。事前の公演案内に、
作者・平松れい子が、アルゼンチン作家「ホルヘ・ルイス・ボルヘス」の幻想小説に触発されて書き下ろした本作品。
熊谷知彦ソロ・パフォーマンス『枝分かれの青い庭で』
とあり、ボルヘスの何だろう? と検索してどうやら「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」らしいと知れたので『伝奇集』所収のそれを読み返した。あはは、あははと読む。
■で、その「トレーン、ウクバール、〜」だけれども、ほんとうに面白い。いま、わたしは『枝分かれの青い庭で』のことを差し置いて、「トレーン、ウクバール、〜」の面白さをこそ触れて回りたい衝動にかられているほどで、ひょっとするとわたしは近々会う人たちにたいし、あたかも最近見つけた面白いインスタアカウントでも教えるような調子で、このボルヘスの短篇のことを紹介しはじめてしまうかもしれないが、しかし、はたしてそんなことが可能だろうか。すでに極限にまで〈要約〉されて語られているようなあの小説を、さらにかいつまんで語るというようなことが。
■さて『枝分かれの青い庭で』は内容的には、「たった一冊の百科事典のなかにだけ発見される『ウクバル』なる項目」というその一点にボルヘスの短篇の痕跡が認められるだけで、それ以外はほとんど「トレーン、ウクバール、〜」と無縁の物語世界が構築されているが、そうでありながら、じつにボルヘス的な仕掛けに満ちてもいる。
■冒頭、開演前の案内(携帯電話の音が出ないようにとか、場内の室温は大丈夫かといったようなこと)を作・演出の平松さん自身がしゃべっているところへ熊谷さんが入ってくる。長机と椅子とがあるその演技エリアはちょっとした DJブースのようになっているのだが、「熊谷さんにはちょっと機材チェックなどしていただいて」という平松さんの説明が入ることで、いまはまだ〈開演前〉なのだという強い了解が作られる。そうして熊谷さんが準備をしているあいだの時間をつなぐように、平松さんが熊谷さんに世間話を仕掛けるのだが、その会話は熊谷さんの俳優としての来歴、平松さんとの関わり、そして俳優業のかたわらでずっと続けてきたさまざまな派遣の仕事のことへと移っていって、やがていま現在派遣されている職場の話に行き着く。たとえそこに紛れ込んでくる事実との齟齬に気づかなかったとしても(というのはつまり、熊谷さんのじっさいのプロフィールや近況を知らなかったとしても)、まあ、次第になんとなく、熊谷さんの饒舌ぶりなどから、あ、これは〈はじまってる〉んだなと気づくバランス(ないしアンバランス)になっているのだが、このようにして巧みに仕立て上げられるところの〈俳優・熊谷知彦という語り手〉こそが、まさにボルヘス的語り──作家であるボルヘス本人の一人称が装われつつ、しかしどこからどこまで(どの固有名詞まで)がほんとう(実在)なのかわからない、ノンフィクション的な枠組みを用いてリアリズムの否定に挑む語り──の立体的な表れとして、まず、ある。
■ちなみに、受付時に配られる簡素な当日パンフレットには挨拶文や物語の導入となるような案内がいっさいなく、代わりに熊谷さんと平松さんそれぞれのやや詳しめのプロフィールが書かれてあるだけなのだが、これもまたおそらく、冒頭部の仕掛けに寄与する伏線として周到に用意されたものだろう。というのは、そこにある熊谷さんのプロフィールを事前に注意深く読んでいれば冒頭部の会話に現れる〈事実との違和〉に気づきやすいということがまずあるからだが、さらに言えば、冒頭部を経て終演後にふたたびこの〈真のプロフィール〉に戻ってきたとき、むしろ、〈この真のプロフィールははたしてどこまでが真なのだろうか〉というような、とぼけた不安定さを覚えさせられるからでもある。
■これはけっきょくツイートしなかった感想だけれど、観終わった直後の「下書き」では、作品の印象はまずこういう驚きとしてわたしの口(指)を衝いた。
- 15:02
- 物語からもっとも遠く離れた「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」から着想を得て、こんな紛れもない物語が紡がれるとは。というような、『枝分かれの青い庭で』。
けれど、投稿する前に読み返してみて、いったい「物語」という言葉が何を指しているのかわれながらよくわからなくなり、語用上の厳格さに欠けるというか、何か言い当てられていないような気がして思い直す。
■それで、『詩という仕事について』というボルヘスの講義録から「物語り」と題された章を読んだのはたんに「物語」という言葉からのつながりだが、まあ、さして思考の整理が付いたわけでもない。それどころか、思考はさらに派生して収拾の目途がなく、たとえば、ボルヘスの語る次のような詩人の姿に、ついつい舞台上の熊谷さんを重ね合わせたくもなってしまう(この講義でボルヘスが扱っている「物語」は、直接的には「叙事詩」のことだ)。
詩人たちは忘れているようですが、ある時期まで、物語を語ることこそが本質的なことであり、その物語を語ることと詩を口ずさむことは別の事柄とは見なされなかったということです。ある人間がある話を語り、それを歌う。聞き手たちは彼を、二つの仕事を試みる人間とは思わなかった。むしろ、二つの側面を有する一つの仕事をしている人間と考えた、あるいは、二つの側面など端から無いと考えた、いやむしろ、その全体を一つの本質的なものと考えたのでしょう。
J. L. ボルヘス『詩という仕事について』「 3 物語り」(岩波文庫)、p.75
■「トレーン、ウクバール、〜」に戻れば、まあ、やはりひとつの肝となるのは「フレニール」(とさらに無説明に出てくる「フレーン」笑)をめぐる記述だろう。
何世紀にもわたる観念論の支配は、現実に影響せずにいなかった。〔…〕二人の人間が一本の鉛筆を捜している。第一の人間がそれを見つけ、何にもいわない。第二の人間が、これに負けないくらい本物らしいが、しかし彼の期待にいっそうぴったりした第二の鉛筆を発見する。これらの第二の物体はフレニールと呼ばれ、形がくずれているが少々長めである。〔…〕トレーンにおいては事物はみずからを複製する。同様に、人々に忘れられると輪郭が薄れ、細部が消える傾きがある。乞食が来ているあいだはそこにあり、彼が死ぬと同時に消えた戸口は、その古典的な例である。時には、数羽の鳥や一頭の馬が円形競技場の廃墟を救った。
J. L. ボルヘス「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」、『伝奇集』(岩波文庫)、p.31-33、太字強調は原文
派生の各段階において周期的な特徴と差異をもつフレニールの、その増殖と現実世界への侵食が語られるとき、トレーンは宇宙の完全な鏡像となって、その円環が完成する──「わたしのウクバール発見は、一枚の鏡と一冊の百科事典の結びつきのおかげである」「世界はトレーンとなるだろう」。序盤に出てくるトレーンが、ウクバール国の文学が生み出した「架空の地方」のひとつと説明されるのにたいし、そののちに再登場するトレーンがひとつの「宇宙」(架空の惑星)として解説されることの齟齬は、つまり、それぞれがともに、別々の〈フレニールとしての現れ〉なのだと考えれば何も不思議はない。
■『枝分かれの青い庭で』もまた同様に、ボルヘスの短篇から派生/複製された紛うことなきフレニールなのだと、考えれば考えるほど、そんな思いに囚われていく。
■と、ここまで、『枝分かれの青い庭で』の直接的な中身にはすっかり触れないまま来てしまったが、どうも熊谷さんは「再演する気満々」であるらしいから、中身にはぜひ、またべつのその庭で出会ってもらえたら幸いだ。
関連記事
トラックバック(0)
このエントリーのトラックバックURL:
https://web-conte.com/blue/mt-tb.cgi/1306